東京の市電から降りる乗客と、乗る順番を待つ乗客。
この写真が撮影された1934年には、東京の市電路線は大きく広がっていて、非常によく利用されていた。この写真に写っている乗客の数からもそれがわかる。
東京で馬車鉄道が開業したのは1882年6月25日。市街電車が電化されたのは1903年8月22日。会社の名前も東京馬車鉄道から、東京電気鉄道(東電)に変わった。最初の路線は新橋―品川間。
1906年には、東電、東京市街鉄道(街鉄)、東京電気鉄道(外堀線)が合併して東京鉄道(東鉄)となった。1911年、東京市がこの東鉄を買収して東京市電と改名。1943年には、東京市が廃止されて東京都制が施行されたのに伴って、東京都交通局に改組し東京都電となった。
最盛時、都電は41路線、総延長は213キロに達した。しかし自動車の普及につれて、乗客数は減り、1967年から1972年の間に181キロの路線が廃止された。
1974年に、残っていた路線を都電荒川線に統合し、完全廃止は免れた。
1990年以降、東京都電の前途にやや好転の兆しが見え始める。この年28年ぶりで新型車両を導入。10年後には停留所の新設(荒川一中前)があり、2007年には再度新型車両が導入された。1
このスライドは、ニューヨーク州教育局が、生徒に日本のことを教えるために作成した、一連の日本のスライドの中の一枚。
脚注
1 ウィキペディア, 東京都電車。2008年2月21日検索
公開:
編集:
引用文献
ドゥイツ・キエルト()1934年の東京・市街電車の乗客、オールド・フォト・ジャパン。2025年11月17日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/135/shigai-densha)
ライセンス可能
この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。
写真番号:80122-0016


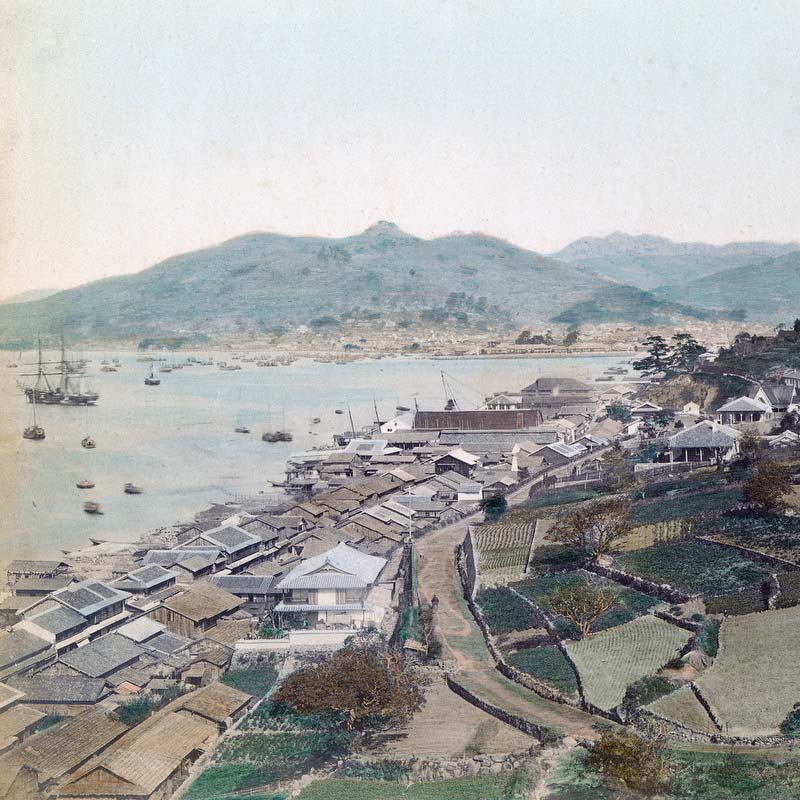
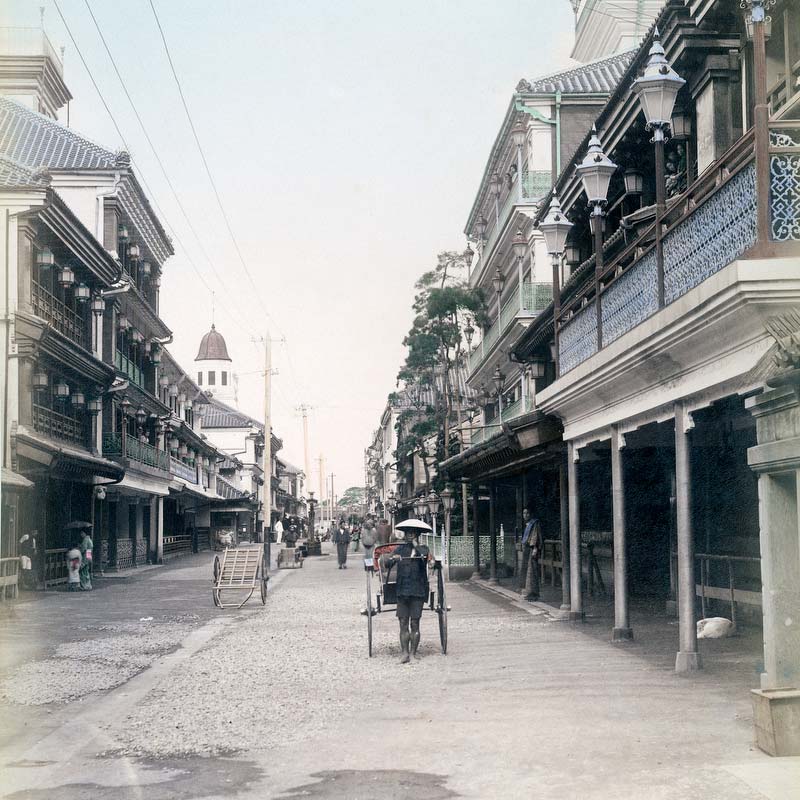
この記事のコメントはまだありません。