祇園祭でよく知られている八坂神社と、巨大な木造の舞台で知られている清水寺の間に、この46メートルの八坂の塔がある。
この塔は一本の木製のシャフトを中心に建てられている。塔の正式な名は法観寺で、聖徳太子(573~621)の創建になるこの寺は、嘗ては東山一帯に広大な面積を占めていた。現存するのはこの塔のみだが、この辺りの小さな家々の間に誇り高く建っている。
1179年に清水寺と八坂神社の間で争いが起こった際、この塔は焼き払われた。1191年にこの塔が再建されたのは将軍源頼朝(1147~1199)の命による。しかし、1291年と1436年には火災に遭い、現存する塔は将軍足利義教(1394~1441)が1440年に建てたもの。
この塔は京都で私の好きなものの一つ。ツーリストの主なルートからは少し離れているので、通りを歩いている内に独りでに塔の前に出ることが多い。残念ながら、京都のシンボルとして有名であるのに電線がこの眺めを壊している。しかし、近くの通りでは電線を地下に埋める工事が進んでいるから、塔の眺めも昔に戻る希望はある。
八坂の塔は浮世絵にもよく描かれている。
公開:
編集:
引用文献
ドゥイツ・キエルト()1910年代の京都・八坂の塔、オールド・フォト・ジャパン。2026年01月25日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/511/yasaka-no-to)
ライセンス可能
この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。
写真番号:70419-0006

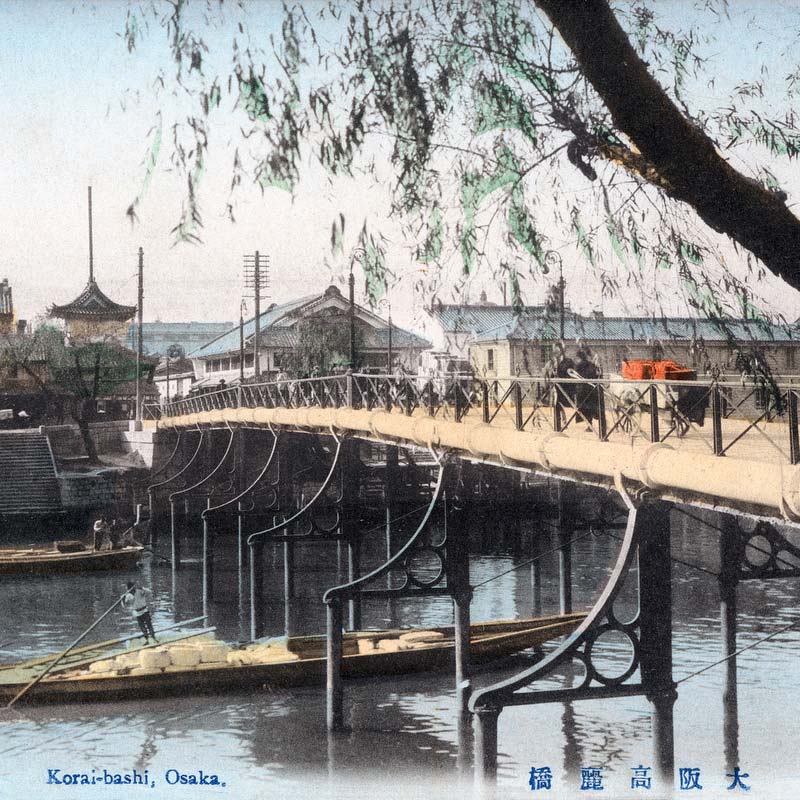


この記事のコメントはまだありません。