京都島原の太夫(高級娼婦)の写真。島原は京都で認められていた遊郭。太夫が着る豪華な衣装は、江戸時代(1603年~1868年)に益々派手になった。
太夫は、舞妓や芸者とは髪型で区別される。この髪形は兵庫と呼ばれ、結うのに何時間もかかる。
前髪は大きな鼈甲と八つの笄で飾る。後ろ髪には六つの前びら、留めと花飾りを差す。重さは全部で3キロにもなる。
太夫の履物は髪型と同様に豪華で、高い黒漆の下駄を履く。普通の下駄の歯は二本だが、太夫が街を歩く時に履く下駄は三本歯である。歩く早さは信じられないくらいゆっくりしたもので、よちよち歩きである。大勢の付き添いに囲まれ、大変な注視の的になる。(吉原道中のプリント参照)
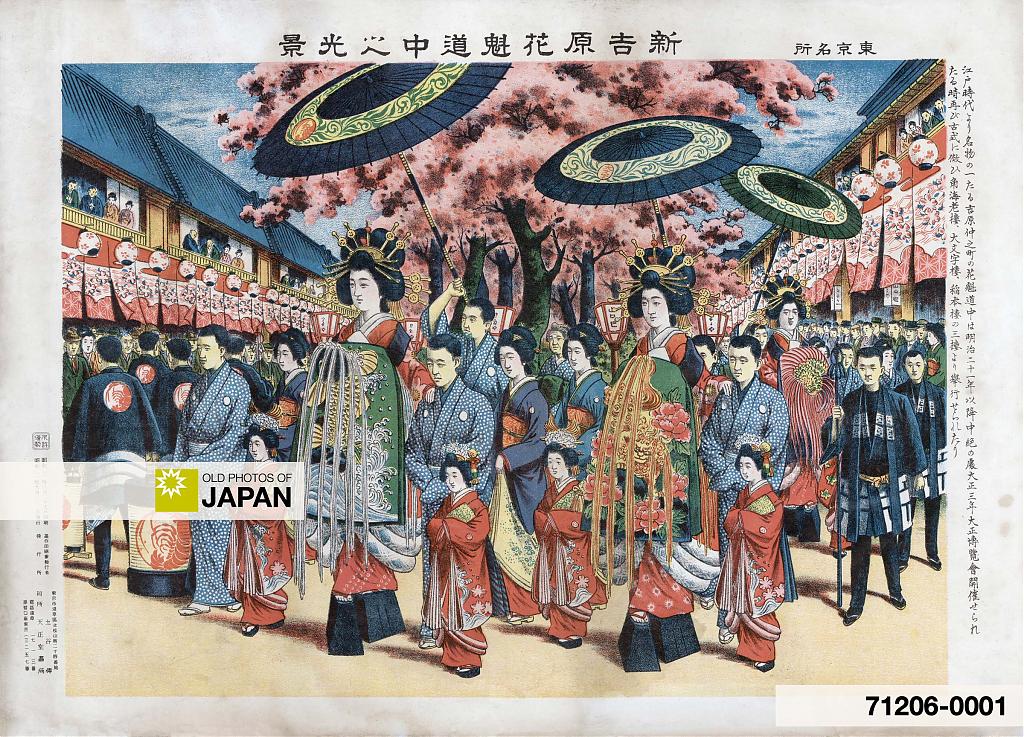
現役の太夫はかなり前に姿を消したが、島原には太夫の文化を活かして継承している女性が4人いる。その一人が司太夫で、島原文化の再生に努めている。
売春は日本では江戸時代(1603年~1868年)に広がった。これを統制するために、徳川幕府は特定の地区を指定した(傾城町)。 中でも有名なのは、江戸の吉原(1617年にできた)1、大阪の新町(1624年から1644年にできた)2、 と京都の島原(1640年にできた)3。
島原は1958年(昭和33年)に新しく法律が施行されて売春が禁止されるまで続いた。残っているのは殆どない。大門は今でも見られるし、昔の島原のお茶屋で元禄年間(1688年~1704年)にできた輪違屋は、太夫文化を紹介する博物館になっており、文化遺産になっている。もう一軒残っているお茶屋は角屋。
脚注
1 De Becker, J. E. (1899). The Nightless City or the History of the Yoshiwara Yukwaku. Max Nössler & Co.
2 Avery, Anne Louise (2006). Flowers of the Floating World: Geisha and Courtesans in Japanese Prints and Photographs, 1772–1926 (Sanders of Oxford Exhibition Catalogue)
3 京都島原の門にある市の公式看板
公開:
編集:
引用文献
ドゥイツ・キエルト()1920年代の京都・島原太夫、オールド・フォト・ジャパン。2025年11月08日参照。(https://www.oldphotojapan.com/photos/175/shimabara-tayu-jp)
ライセンス可能
この写真はライセンスも可能です。ストックフォト(写真素材)を専門とするエージェンシーMeijiShowa(明治昭和)では、 明治、大正、昭和初期にかけてのアーカイブ写真・イラスト・ならびに古地図を、 エディトリアル・広告・パッケージデザインなどのライセンスとして販売しております。
写真番号:70510-0002



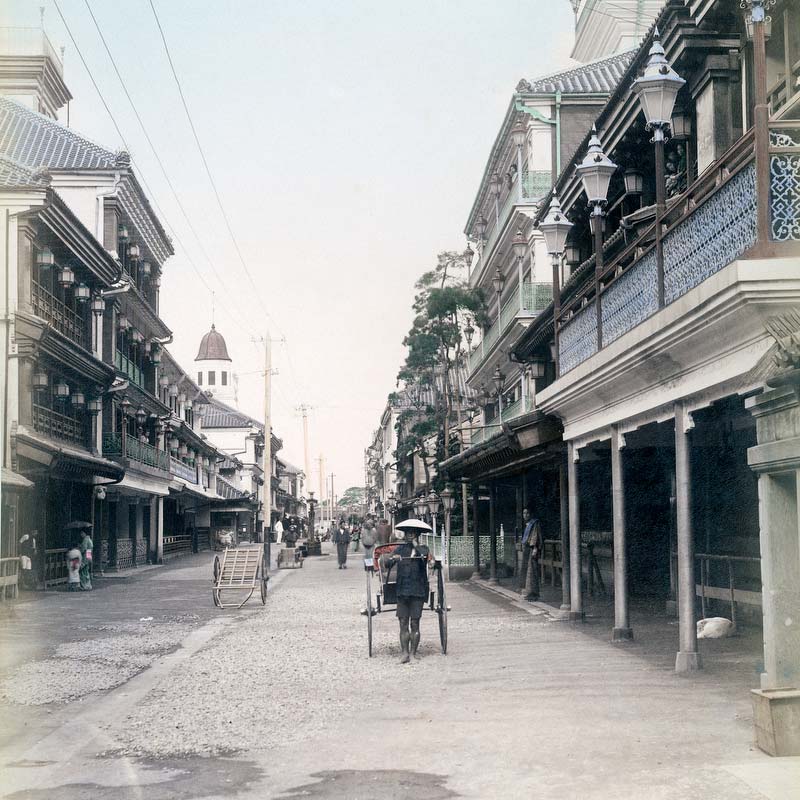
琵琶(嶋原応援してます)
はじめまして、検索にてたどりつきました。
京都の島原(嶋原)の文化を太夫さんを支持・応援
しているものです。
太夫さんは、売春婦という言葉では表現できませんし、
単なる芸妓というわけでもなく、とても特異な存在だった
ようです。特に京嶋原は公卿の遊び相手の女性と
しての傾城・太夫であり、独特の文化が生まれ、
他の京の花街のお手本ともなっていたようです。
上の記事の文章に少し誤りがあると思うのですが・・
輪違屋さんは、現在も現役の「お茶屋」として営業中です。
太夫の置屋でもあり、太夫をお座敷に上げて、芸を見せるのは
今ではこちらのお店だけです。
芸を見せるため現在でも太夫さん
(今では3人になりましたが)方は
舞・茶道を必須として
和楽器・唄・書道・香道 といった芸教養、
お客さんへの接客 を日々磨いておられます。
また、「角屋」さんは現在は美術館として
かつての嶋原文化の紹介・普及を行っておられます。
今後もこのような嶋原の文化が大切に受け継がれていくことを
望んでいる者です。
#000035 ·
通りすがり
二枚目の写真は吉原のものだと思われます
訂正をお願いします
#000635 ·